「ママ、犬を飼いたい!」「パパ、お友達のワンちゃんが可愛かったから、うちでも飼おうよ!」
子供からのこんな言葉に、親としてどう応えるべきか悩んでしまいますよね。可愛い愛犬との生活は確かに素晴らしいものですが、「可愛いから」だけで始められるほど簡単ではないのも事実です。
子供の純粋な気持ちを大切にしながらも、家族全員にとって幸せな判断をするために、年齢別の判断基準と事前に家族で決めておくべき約束事について、一緒に考えていきましょう。
1. 子供の「犬を飼いたい」の背景を理解する
よくある「きっかけ」
友達の家で犬と触れ合った お友達の家で犬と遊んで、その楽しさや可愛さに心を奪われるパターン。特に人懐っこい犬と触れ合った後は、子供の「飼いたい」気持ちが最高潮に達することが多いですね。
テレビや本で犬を見て憧れた 映画やアニメ、絵本に出てくる犬への憧れから「飼いたい」と言い出すケース。創作物の犬は実際の犬とは大きく異なることも多いため、現実との違いを理解させることが重要です。
「一時的な憧れ」か「本気の気持ち」かを見極める
継続性をチェック 犬を飼いたいと言い出してから、どのくらいその気持ちが続いているかを観察してみましょう。一週間後にも同じことを言っているか、犬に関する本を読んだりしているかなど。
具体的な質問をしてみる 「犬のお世話って、どんなことをすると思う?」「毎日お散歩に行くのは大変だと思うけど、大丈夫かな?」といった質問をして、子供がどの程度現実的に考えているかを確認します。
現在の責任感を観察 今の年齢に応じた責任(お手伝い、宿題、身の回りの整理など)をきちんと果たせているかも、重要な判断材料になります。
2. 年齢別の判断基準と期待できること
どの年齢でも共通する大前提
犬は家族の一員 – みんなで世話をする まず最初に家族全員で共有しておきたいのは、「○○ちゃんが飼いたいと言ったから○○ちゃんの犬」ではないということ。犬は家族の一員となり、家族みんなにとって大切な存在になります。
世話も同様で、子供だけに押し付けるものでも、親だけが背負うものでもありません。子供の年齢や能力に応じて役割分担はしますが、基本的には「家族みんなで協力して世話をする」という考えが重要です。
3-5歳(幼児期):基本的には「まだ早い」
現実的な判断 この年齢で犬を飼う場合、実際の世話は完全に親の責任になります。子供は「可愛がる」ことはできても、「責任を持って世話をする」ことは期待できません。
子供ができること
- 犬と優しく遊ぶ
- 簡単なお手伝い(フードを入れる、ブラッシングなど)
判断基準 両親が「自分たちが主体となって世話をする覚悟」があり、かつ子供が動物に対して優しく接することができる場合のみ検討可能。
6-8歳(小学校低学年):「お手伝い要員」として参加
期待できること 基本的な世話は親が行い、子供には年齢に応じた「お手伝い」をしてもらうレベル。家族みんなで犬を世話する感覚を少しずつ身につけていく時期です。
子供ができること
- 決められた時間に食器にフードを入れる
- 家族と一緒に散歩に行く
- 毎日のブラッシング
- 犬の様子を観察して報告
判断基準
- 基本的な生活習慣が身に


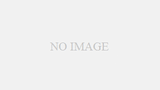
コメント